砂糖がなぜ食品の保存に使われるのか?その科学的メカニズム
1. 砂糖を控えた食品で起きた事故の背景
近年、健康志向の高まりから「防腐剤不使用・砂糖少なめ」の食品が増えています。しかし、これが予期せぬ問題を引き起こすこともあります。
例えば、以前にイベント会場で販売した焼き菓子を食べた人達が腹痛や吐き気を訴える事故が発生しました。その際、「腐った臭いがする」「糸を引く」といった報告も相次ぎました。原因は砂糖を大幅に減らしたことによる保存性の低下でした。砂糖は甘さを加えるだけでなく、食品の保存性を高める重要な役割を持っています。
今回のコラムでは、その科学的メカニズムについて詳しく見ていきましょう。
2. 砂糖の役割は甘味だけじゃない?
「砂糖=甘い」というイメージが強いですが、実はそれだけではありません。 砂糖には、食品の保存性を高める重要な働きがあり、私たちの食生活に欠かせない存在なのです。たとえば、ジャムや羊羹(ようかん)、ドライフルーツなど、長期間保存できる食品には砂糖が多く含まれています。これは、砂糖が持つ「吸湿性」や「浸透圧」の特性が関係しているからです。
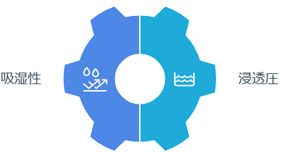
3. 砂糖の吸湿性とは?
砂糖は水分を引き寄せる「吸湿性」を持っています。
これは、食品内部の水分を外に逃がさずに保ち、乾燥や劣化を防ぐ働きをします。
例えば、以下の食品は、砂糖を入れることで食品の水分が保たれます。
- 焼き菓子 → 砂糖が水分を保持し、しっとり感を維持
- パン → 砂糖が水分を保持し、パサつきを防ぐ
- 和菓子(羊羹・練りきりなど) → 長期間しっとりとした食感が続く
よって、砂糖を減らしすぎると、水分が逃げてしまい、食品が固くなったり、パサついたりする原因になります。

4. 砂糖の「浸透圧」で食品が長持ちするしくみ
砂糖が食品の保存に使われる大きな理由のひとつが、「浸透圧」の作用です。
浸透圧とは?
水分は、濃度の低い方(薄い溶液)から濃度の高い方(濃い溶液)へ移動する性質があります。この水分移動を引き起こす圧力を「浸透圧」と呼びます。
微生物の細胞は水分がないと生きられません。食品中の糖濃度が高くなると、浸透圧の作用で微生物の細胞から水分が奪われ、活動できなくなります。これが、砂糖による「保存効果」の正体です。
なお、梅干しや漬物などに使われる塩による保存は、より身近な例かもしれません。塩も同様に浸透圧の作用で微生物の水分を奪いますが、塩の場合は細胞を強く脱水・破壊する力があるため、食品が乾燥しやすくなるという特徴があります。
下表のとおり、砂糖と塩の浸透圧の作用と食品例をまとめてみました。砂糖は水分を保ちながら保存できるため、しっとりとした食感も保ちやすくなるのがイメージできると思います。
| 保存方法 | 作用 | 食品例 |
| 砂糖漬け | 浸透圧で微生物から水分を奪う | ジャム、甘露煮 |
| 塩漬け | 浸透圧+強い脱水作用 | 梅干し、漬物、塩漬け肉 |
また、糖濃度と保存性の関係を表したのが、以下の表です。糖度が高いほど保存性が高まり、低すぎると傷みやすくなることがわかります。
| 食品 | 糖分濃度 | 保存期間の目安 |
|---|---|---|
| ジャム | 60~70% | 数か月~1年以上 |
| 甘露煮 | 約30% | 1か月以上 |
| 佃煮 | 15% | 2週間~1か月 |
| 煮物(薄味) | 3~5% | 2~3日 |
浸透圧の効果を活かすには?
📝 糖度60%以上で保存性アップ
📝 酸や冷凍保存との組み合わせも有効(例:ジャム+レモン、冷凍低糖ジャム など)
5. 砂糖控えめで気をつけたいことと、その工夫
「砂糖を控える」こと自体は健康に良いのですが、食品の保存性を高める工夫が必要です。
💡砂糖を減らしたときに起こりやすいこと
- 微生物の増殖 → 砂糖濃度が低いとカビや細菌が繁殖しやすい
- 食感や風味の低下 → 保存中に水分が失われ、食品が固くなる
- 保存期間の短縮 → 早く食べないと傷みやすい
💡砂糖を控えたときに、保存性を保つためにできること
- 冷蔵・冷凍保存を徹底する → 低温で微生物の増殖を抑える
- 酸(レモン果汁・お酢)を加える → 酸性環境では微生物が繁殖しにくい
- 低糖ジャムにはペクチンを追加する → 食感を保持しやすくなる
6. 砂糖の役割のポイント
- 砂糖は甘さを加えるだけでなく、保存性を高める重要な役割を持つ
- 吸湿性により食品の水分を保持し、しっとり感を維持する
- 浸透圧により微生物の活動を抑制し、食品を安全に保つ
- 砂糖を減らしすぎると、保存性が低下し、食品が傷みやすくなる
- 酸を加える・冷蔵保存するなどの工夫で、低糖レシピでも安全に保存できる
「砂糖=不健康」という誤解をなくし、適切に活用して食品を美味しく、安全に保存しましょう!
参考資料
- 農林水産省 砂糖のすべて ~原料の生産から製品まで~ 令和4年5月 https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/kanmi_sigen/attach/pdf/index-3.pdf
- 似て非なるもの塩と砂糖の不思議 Q&A <塩と砂糖の歴史> https://www.shiojigyo.com/institute/upload/papers_16_52-59.pdf


