砂糖税入門 ― 世界で広がる“甘さのルール”をわかりやすく解説
1. はじめに:なぜ“税”が甘さ対策になるのか?
ここ数回のコラムでは、飲料のラベルから砂糖量を換算する方法(2025年8月26日号)、異性化糖と砂糖との違い(2025年9月2日号)、日本発の技術史(2025年9月9日号)、そして私たちが日常的に口にする自由糖の摂取源(2025年9月16日号)を紹介してきました。
いずれも「自分がどれだけ糖を摂っているのか」を、身近な生活の中で意識できるようになることをねらいにしてきました。
今回からは少し視点を広げ、個人の工夫だけではなく「社会全体で砂糖摂取を抑える仕組み」に目を向けます。具体的には砂糖税と呼ばれる制度です。
「税」と聞くと難しく感じるかもしれません。しかし砂糖税は、すでに世界各地で導入され、肥満や糖尿病といった健康問題への対策として機能しています。価格を上乗せすることで消費を減らすと同時に、メーカーに「砂糖を減らした商品づくり」を促す役割もあります。
私たちが毎日飲んでいる清涼飲料水や加糖飲料。その1本がもし「少し高くなる」としたら、選び方や飲む頻度が変わるかもしれません。そうした行動変化をねらった制度こそが砂糖税なのです。
2. 砂糖税の3つのねらい ― 健康・行動・税収
砂糖税が導入される背景には、大きく3つの目的があります。
① 公衆衛生の観点
砂糖の過剰摂取は、肥満や糖尿病、心血管疾患などのリスクを高めることが、多くの研究で明らかになっています。そこで各国は、砂糖を含む飲料や食品に税をかけることで、国民の健康リスクを少しでも減らそうとしています。医療費の増大を防ぐという側面も大きな狙いです。
② 行動変容の観点
税によって価格が上がれば、消費者は自然に「少し控えよう」と考えるようになります。さらに、メーカー側も「砂糖を減らした商品に作り替える」動機づけとなります。結果として、市場全体の砂糖摂取量を下げる効果が期待できるのです。
③ 財源の観点
砂糖税によって得られた税収は、単に政府の収入になるだけではありません。多くの国では、その財源を子どもの栄養教育や健康増進プログラムに活用しています。つまり、税は“罰則”ではなく、社会に還元される仕組みでもあります。
このように、砂糖税は「健康を守る」「行動を変える」「得られたお金を再投資する」という3つの役割を担っています。単なる負担増ではなく、社会全体の健康を底上げするための仕組みと理解すると、その意味が見えてきます。
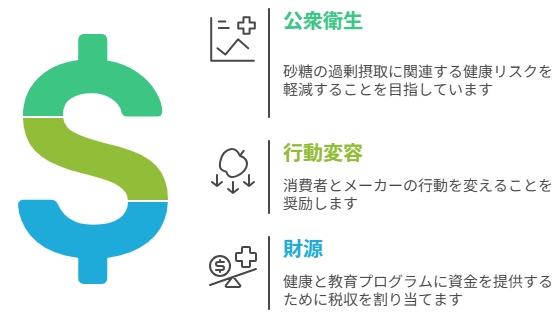
3. どう課す? 世界で使われる方式のちがい
砂糖税とひと口に言っても、国や地域によって設計の仕方はさまざまです。
「消費者に何を期待するのか」「メーカーにどう動いてほしいのか」によって、かけ方が工夫されています。ここでは代表的な3つの方式を紹介します。
① 容量課税(1本あたり)
飲料の容量そのものに税をかけるシンプルな方法です。消費者にとっては「1本あたり数円〜数十円高くなる」というわかりやすい仕組みです。米国では連邦レベルでの導入はありませんが、バークレー市やフィラデルフィア市など都市単位で実施されています。
② 糖濃度課税(段階課税)
飲料に含まれる砂糖の量に応じて税がかかる方法です。砂糖が多い飲料ほど税が高くなるため、メーカーは砂糖の使用量を減らす工夫をするようになります。イギリスの「ソフトドリンク産業税」が代表例です。
③ 従価課税(販売価格に対して)
商品の販売価格に一定の割合で税をかける方法です。高価格の商品では税額が大きくなるため、消費者の負担に差が出やすいという特徴があります。幅広い食品に対応できますが、負担の感じ方には差が生じます。
💡 補足:清涼飲料の定義の違い
国や制度によって対象範囲は異なります。日本の「清涼飲料水」は非常に広い範囲を含みますが、イギリスや米国では砂糖を加えた飲料(炭酸飲料、加糖茶、エナジードリンクなど)が対象で、100%果汁や牛乳系飲料は除外される場合が多いのが特徴です。
方式ごとの長所・短所(まとめ)
| 方式 | 長所 | 短所 |
| 容量課税(1本あたり) | シンプルでわかりやすい | 砂糖の多い少ないに関係なく同じ税額 |
| 糖濃度課税(段階課税) | 砂糖の多い商品を強く抑制できる | 制度がやや複雑 |
| 従価課税(価格に対して) | 幅広い商品に対応可能 | 高価格品に負担が偏りやすい |
4. 導入国をのぞく ― メキシコ・イギリス・米国都市・アジア
砂糖税はここ10年ほどで世界に広がり、特に砂糖入り飲料を対象とした制度が多く見られます。導入の背景にはそれぞれの国や地域ならではの事情があり、方式の違いも「どの課題を優先するか」によって選ばれています。
ここでは代表的な事例として、消費者行動に大きな変化をもたらしたメキシコ、メーカーの対応を引き出したイギリス、地域レベルで取り組む米国の都市、そして急速に制度を広げるアジア各国を取り上げます。最後に日本の現状も簡単に整理します。
メキシコ(容量課税) ― 消費者行動の変化
2014年に導入。飲料1リットルあたり約1ペソを課税。砂糖入り飲料の購入が減少し、水や無糖飲料に置き換える動きが見られました。
イギリス(糖濃度課税) ― メーカーの改革を促す
2018年に導入。糖度5g/100mL以上で課税、8g/100mL以上で高税率。メーカーが砂糖量を減らした商品を投入し、市場に大きな影響を与えました。
米国(都市単位) ― 地域発の取り組み
国全体ではなく、バークレー市(2014年)、フィラデルフィア市(2017年)などが導入。地域レベルの取り組みですが、一定の効果が確認されています。
アジア(タイ・マレーシアなど) ― 急速に広がる導入
経済成長とともに飲料消費が増えた背景から、2017年以降に相次いで導入。糖濃度課税を採用する国が多く、段階的に税率を引き上げています。
日本の現状 ― 自主的取り組みにとどまる
砂糖税は導入されておらず、メーカーの自主的な砂糖削減の取り組みが中心となっています。
国際的には砂糖税が広がっていますが、日本では制度化には慎重な姿勢がとられているのが現状です。
5. 砂糖税をめぐる誤解とホントのところ
砂糖税という言葉を聞くと、「結局、税金を取られるだけでは?」と感じる方も少なくありません。そこで、よくある誤解と実際のところを整理してみましょう。
Q1. 経済に悪影響では?
「砂糖税が導入されると飲料メーカーの売上が落ち、経済が停滞するのでは」と言われることがあります。ところが実際には、メーカーは砂糖を減らした商品や無糖飲料を新しく開発し、市場が活性化した例もあります。また、税収を健康教育や医療費削減に充てることで、長期的には社会全体の負担軽減につながります。
Q2. 人工甘味料に置き換えれば健康的?
砂糖を減らした分、人工甘味料を使った飲料が増えるのではと懸念する声もあります。人工甘味料は血糖値に影響しにくい一方で、摂取習慣や味覚への影響が議論されています。砂糖税の目的は「砂糖を完全になくすこと」ではなく、全体の摂取量を減らす工夫を促す点にあります。
Q3. 自由な選択を制限していないか?
砂糖税は「禁止」ではありません。消費者が選べる自由は残しつつ、「価格」という形で控えるきっかけを与える制度です。むしろ、健康的な選択肢を選びやすくするための社会的サポートだと考えることができます。
6. 砂糖税がもたらした変化 ― 行動・商品・社会
実際に砂糖税を導入した国や地域では、さまざまな変化が報告されています。
① 消費者の行動変化
メキシコや米国の都市部では、砂糖入り飲料の購入量が減り、水や無糖飲料に置き換わる動きが見られました。
② メーカーの製品改革
イギリスでは、飲料メーカーが砂糖を減らした製品を開発し、市場に新しい選択肢が広がりました。
③ 税収の活用
集められた税金が教育や健康事業に使われる例もあり、社会に還元される仕組みが作られています。
ここでは概要だけを紹介しましたが、これらの効果については研究や統計で具体的に検証されています。一人ひとりの選択の積み重ねが、未来の健康を形づくるのです。
次回は「実際にどのような成果や課題が明らかになったのか」を、各国のデータをもとに掘り下げていきます。
参考資料
- 世界保健機関(WHO) (2016). Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases
https://www.who.int/docs/default-source/obesity/fiscal-policies-for-diet-and-the-prevention-of-noncommunicable-diseases-0.pdf?sfvrsn=84ee20c_2%20 - M.C. Fernandes, et al. (2025). Effectiveness of sugar taxation policies in Asia and Africa. Public Health Nutrition, 28(1), 1–14.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12014706/


