水の科学 ― みずみずしさとおいしさの境界で
1. はじめに― みずみずしさは“おいしさのサイン”
「みずみずしい」という言葉ほど、食べものの魅力をうまく表す言葉はありません。
切ったばかりのトマトのつや、炊きたてご飯の光沢、ゆでた野菜の鮮やかな色――
それらはすべて、食材の中に“ちょうどよくとどまった水”がつくるものです。
水は、味や香りを運び、口の中で食感をつなぐ存在です。
多すぎても薄まり、少なすぎてもかたくなる。
おいしい料理とは、水をほどよく抱え、上手に“動かす”料理といえます。
料理の世界での水の役割は実に多彩です。
洗う、煮る、だしをとる、戻す――どれも水がなければ成り立ちません。
干し椎茸を水で戻すと、時間とともに香りとうまみが広がっていきます。
そのうまみ成分「グアニル酸」は、水に浸けているあいだに酵素の働きで生まれます。
つまり、水は単に“溶かす”だけでなく、おいしさを生み出す場でもあるのです。
また、水は味そのものの感じ方にも関わっています。
練り羊かんと水羊かんを比べると、糖の量は半分以下なのに、水羊かんのほうが甘く感じられませんか?
これは、水が多く流動性が高いため、呈味成分が舌の味蕾(みらい)に届きやすくなるからです。
つまり、水は味を伝える**橋渡し役**です。
水の量と流れ方が、私たちの“おいしい”の感じ方を決めているのです。
一方で、その“おいしさの源”である水は、時間とともに姿を変えます。
冷めるとパサつくご飯、冷凍後にすの入った豆腐――
わずかに水が動くだけで、食べものの印象はがらりと変わります。
今回のテーマは、「水がおいしさを生むしくみ」。
みずみずしさの裏にある科学を通して、
日々の料理が少し違って見える“水の世界”をのぞいてみましょう。
2. 食材の中の水は“味と食感”を決めている
食材の中の水は、ただの「水分」ではありません。
その存在のしかたが、食感や口当たり、みずみずしさを左右します。
食品中の水には、自由に動ける自由水と、分子にしっかりつかまった結合水があります。
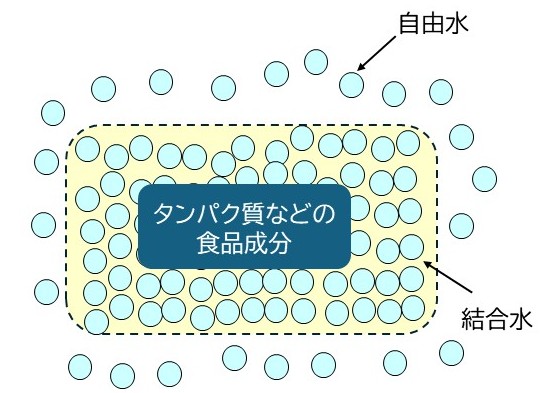
食品中には性質の異なる2種類の水が存在します。
ひとつは、食品成分に結びつかず自由に動ける「自由水」。
もうひとつは、たんぱく質や糖などの分子と強く結びついて動けない「結合水」です。
図1に示すように、結合水は、たんぱく質などの表面に直接吸着した水分子と、その外側に水素結合でつながる数分子の層からなります。
さらにその外側を取り囲むのが、自由水の層です。
この層の構造や割合が、食品のやわらかさやみずみずしさを左右します。
自由水は、口に含んだときに感じるジューシーさや、加熱によって生まれるふくらみ・軽さをつくります。
一方、結合水はたんぱく質や糖などと結びつき、しっとり感ややわらかさを支える「内部の潤い」として働きます。
近年の食品物理学の研究では、水は**可塑剤(plasticizer)**のように、食材の分子構造のすき間に入り込み、
固体をやわらかく、弾力のある状態に変える働きをもつと説明されています。
水が少なすぎると硬くもろく、適度に含まれると“もちもち”“ふんわり”とした食感が生まれる――
つまり、水は単なる成分ではなく、食感を設計する要素なのです。
表1:食品中の自由水と結合水の例
| 分類 | 水の状態 | 食品例 | 特徴 | 食感・印象 |
|---|---|---|---|---|
| 自由水が多い | 分子に束縛されず動きやすい | 果物、野菜、刺身、ご飯 | 水がよく動く | みずみずしい、軽い |
| 自由水がやや少ない | 一部が塩分・糖などに結合 | パン、プリン、卵焼き、チーズ | 適度なバランス | しっとり、ふんわり |
| 結合水が多い | 分子と強く結合して動きにくい | 乾燥果実、練り羊かん、餅 | 構造が密 | 弾力、濃厚 |
| ほぼ結合水のみ | 自由水ほぼなし | チョコ、クッキー、干物 | 安定して乾燥 | サクサク、風味濃縮 |
表1に示すように、自由水と結合水の比率は、食品の味わいと食感の印象を決めています。
自由水が多いほど、私たちは「みずみずしい」「新鮮」と感じます。
一方、結合水が増えると、組織は締まり、しっとり、もちもち、濃厚といった印象に変化します。
こうした違いは、調理の過程でも表れます。
たとえば、焼き立てのパンが時間とともに乾いていくのは、自由水が外へ逃げ、結合水に移り変わるためです。
また、水分量の違いは、味の感じ方にも影響します。
水分の多い食品では、呈味成分が舌の味蕾に届きやすくなり、同じ糖量でも甘みを感じやすくなります。
このように、水の「量」だけでなく「どんな形でとどまっているか」が、食べものの味と質感を決定します。
おいしさを形づくるのは、自由水と結合水のバランス。
その見えない調和こそが、“みずみずしさ”の正体なのです。
3. 台所の浸透圧 ― 水を動かしておいしさをつくる
食材の中の水は、常に動いてバランスを保っています。
塩をふったきゅうりから水が出てくるのも、果物を砂糖に漬けるとシロップが上がるのも、
すべて水が“濃度の差”に引かれて移動するためです。
このしくみを**『浸透圧』**といいます。
この“水の動き”の舞台となるのが、食材の細胞膜です。
外の液体に塩や砂糖が多いと、細胞の中の水は外へ出ようとし、
逆に外が薄いと、水は中へ戻ろうとします。
台所で行うさまざまな操作――塩もみ、砂糖漬け、煮込み、マリネ――は、
じつはこの“水の出入り”を利用しているのです。
たとえば、野菜の塩もみは単なる水抜きではありません。
外側の塩濃度が高くなると、細胞から水がにじみ出て苦味や青臭さが減ります。
同時に、細胞膜がやわらかくなり、噛んだときの歯ごたえがほどよく残ります。
水を引き出すことで、野菜の味が引き締まり、香りが立つのです。
果物を砂糖に漬けると、はじめに水が外へ出てシロップができ、
やがてその一部が果実の中へゆっくり戻っていきます。
この「水の行き来」が、果物をしっとりとした食感に変え、
甘みや香りをなじませます。
水が動くたびに、果物の内と外で、味と香りが再び組み直されていくのです。
煮物やマリネのように味をしみこませる調理でも、
加熱や時間の経過によって細胞膜がゆるみ、味がしみ込みやすい状態になります。
外の調味液が内側へ入り込むのです。
味のしみ方は、塩分・糖分の濃度、温度、時間の組み合わせによって変わります。
料理人はこの加減を直感的に見極め、“水の動き”を操っているのです。
また、塩をまぶしたキャベツがしゃきっとし、
砂糖をまぶした果物がしんなりするのも、
水の移動によって細胞の中の張りの力(ターゴル圧)が変わるためです。
細胞が水で満たされていれば張りがあり、
水が抜ければしなやかでやわらかい食感になります。
水が動くことで、食材の表情は大きく変わります。
おいしさとは、単に調味料の配合だけでなく、
水の出入りをどう設計するかでも決まります。
水を抜けば素材が締まり、水を入れれば味がなじむ――
この繊細な調整こそ、台所に受け継がれてきた“水の技術”なのです。
4. 塩が教えてくれる ― 水を感じる台所の知恵
塩は、料理の中で最も身近な“科学の素材”かもしれません。
ふだん何気なく振るそのひとつまみが、水の流れを変え、味と食感を左右しています。
きゅうりに塩をふると水が出て、魚に塩をすると身が引き締まる。
果物を砂糖に漬けるとシロップが上がる――これらはすべて、浸透圧という自然の力によるものです。
水は濃度の低いほうから高いほうへと移動します。
塩や糖の多い場所は、言わば“水を引き寄せる場所”。
台所では、この力を日々の料理に生かしてきました。
たとえば、野菜の塩もみは単なる“水抜き”ではありません。
外の塩濃度が高くなると、細胞の中の水が外へにじみ出ていき、
同時に苦味や青臭さも抜けていきます。
その結果、食感はほどよく引き締まり、香りが際立ちます。
逆に、煮物やマリネでは“水を入れる”方向に働かせます。
加熱や時間の経過で細胞膜がゆるみ、外の調味液が内側へと染みこんでいくのです。
塩や糖の濃度、温度、時間――その加減を見極めることが、
味のしみ方や食感の決め手になります。
プロは、この加減を直感的に見極め、“水の動き”を操っています。
塩はまた、「いつ振るか」によっても料理を変えます。
たとえば焼く直前に塩をすれば、表面にうま味を閉じ込めてジューシーに。
少し時間をおいてなじませれば、味が全体に広がり、
身がしっとりとした仕上がりになります。
つまり、塩をふるという行為は、水の出入りを設計することなのです。
この“水の設計”を感じ取る感覚こそ、台所の知恵です。
昔の人は科学の理屈を知らなくても、塩や砂糖で水を動かす方法を体で覚えていました。
水を抜いて旨みを凝縮させ、時に戻してやわらかくする――
その積み重ねが、日本の家庭料理の味を育ててきたのです。
料理とは、火だけでなく、水をどう扱うかの技術でもあります。
塩は、水の動きを整える大切な役割を担っています。
ひとつまみの塩が、みずみずしさを引き締め、
おいしさを長く保つための小さな科学を教えてくれます。
💡 次回予告
次回は、この「水の動き」が食の安全や保存性にどのように関わるのかを取り上げます。
冷蔵・冷凍・乾燥といった保存技術を通して、水と時間の関係を科学的に見ていきます。
参考資料
- Blahovec, J. (2007). Role of water content in food and product texture. International Agrophysics, 21(1), 1–12.
- 畑江 敬子(2020)「食べものの“水分”を考える ― みずみずしさと保存性のあいだ」『水の文化』第52号, pp. 12–17. ミツカン水の文化センター.
https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no52/03.html


